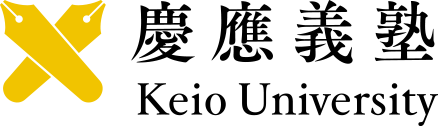文化人類学という学問について、どのようなイメージを持っているだろうか。「未開」の地に足を踏み入れ、現地の人とともに暮らし、彼らの神話・儀礼・呪術の構造や意味を、参与観察を通じて記述する営み。近代文明を生きる「私たち」が、遠い「彼ら」の文化と言語を学び、生かすための活動。西洋人による「知」という名の権力による、非西洋社会の統制と開発。異文化に身を置き、さまざまな声に耳を傾け、場の空気を肌で感じることによって明かされる多様な世界のありようへの気づき。それは自分が当たり前と認識している世界とは全く違う世界があるかもしれないという、無限の可能性への冒険ともいえる。こう連想していくと、文化人類学はそもそも学問という括りには収まらないことがわかる。学ぶこと、観ること、聴くこと、共に生きることそのもののように思えてくる。
私は人類学研究の方法であるフィールドワークを様々な場で実践しているが、近年は「身体的なアプローチとしての一人称フィールドワーク」の可能性を模索している。フィールドワークは、自ら参与し体験していく方法という意味では常に身体的であるが、フィールドワークを通して自分自身の身体と環境との関わりに気付いていくことの面白さを伝えたい。
医療人類学者トマス・ショルダッシュの”Somatic Modes of Attention” 1 (1993)という論文により、人類学において身体への注目が高まってきている。従来の人類学研究では主体と客体が対立され、思考的な注意モードが優勢であったといえるが、ショルダッシュは関心を記号的・象徴的な理解から、経験そのものの理解へとシフトさせている。近年では身体は単なる客体としてではなく、経験する行為体として捉えられている。Somatic Modes of Attention(身体化された注意モード)とは、「私たちの身体に注意を向け、同時に私たちの身体で注意を向けることである。このようなモードは、文化によって象られ、意味づけられている」 (1993, p.138)とショルダッシュは説明している。概念では掴みにくいため、どのようにSomatic Modes of Attention(身体化された注意モード)で実際にフィールドワークを行うかを、授業では具体的なワークを通して探求している。以下は、授業で行うワークの例である。
・日常の行為を身体化された注意モードで観察する:マインドフル・イーティング:
私の声の誘導を聞きながら、受講者はこのようにマインドフル・イーティングを実践する。ワークのあとにはグループでディスカッションを行い、授業後の課題ではさらに言葉で経験を丁寧に記述する。このほか、ゆっくり歩く実践や、目隠しをして気配を感じるワークなど、様々な一人称フィールドワークを授業で試している。
人類学的フィールドワークは、遠い未開の地に出向かなくても、日常のなかで実践できるということが、このようなワークを通して見えてくる。日々、見過ごしていることや、無意識で行っていることに、身体をともなって注意を向けていくと、「近い」ものを通して「遠い」ところへも旅ができるのであり、同時により「近く」、細やかに豊かに経験を味わうことができるだろう。身体的なモードで五感をひらき、一人称フィールドワークを行うと、毎瞬毎瞬を、新たな経験や景色として味わい尽くすことができるかもしれない。
1 Csordas, Thomas. 1993. Somatic Modes of Attention. Cultural Anthropology. Vol.8, no.2, pp.135-156.
私は人類学研究の方法であるフィールドワークを様々な場で実践しているが、近年は「身体的なアプローチとしての一人称フィールドワーク」の可能性を模索している。フィールドワークは、自ら参与し体験していく方法という意味では常に身体的であるが、フィールドワークを通して自分自身の身体と環境との関わりに気付いていくことの面白さを伝えたい。
医療人類学者トマス・ショルダッシュの”Somatic Modes of Attention” 1 (1993)という論文により、人類学において身体への注目が高まってきている。従来の人類学研究では主体と客体が対立され、思考的な注意モードが優勢であったといえるが、ショルダッシュは関心を記号的・象徴的な理解から、経験そのものの理解へとシフトさせている。近年では身体は単なる客体としてではなく、経験する行為体として捉えられている。Somatic Modes of Attention(身体化された注意モード)とは、「私たちの身体に注意を向け、同時に私たちの身体で注意を向けることである。このようなモードは、文化によって象られ、意味づけられている」 (1993, p.138)とショルダッシュは説明している。概念では掴みにくいため、どのようにSomatic Modes of Attention(身体化された注意モード)で実際にフィールドワークを行うかを、授業では具体的なワークを通して探求している。以下は、授業で行うワークの例である。
・日常の行為を身体化された注意モードで観察する:マインドフル・イーティング:
レーズン、くるみ、などの一粒の実を事前に用意してもらう。その食べ物を掌に置き、じっくりと存在を感じ、観察する。まるで宇宙人が初めて地球上のこの食べ物を遭遇したかのように、ビギナーズ・マインド、初心の気持ちで、一粒の恵にこころを向ける。その一粒の実の存在、いのちに、心を合わせる。一粒の実の重たさ、硬さ、冷たさ、唯一無二の形、匂い、音、光のあたり具合、質感などを確認していく。その一粒の実に注意を向ける自分は、どのような経験をしているのか、自分の身体の感覚や、心の変化を観察していく。その実がどのような条件で実り、どのような経緯で今ここ自分の掌にたどり着いたか、に意識を向ける。その実と対話するなかで生起される感情や衝動も観察する。ゆっくりと、実を口元に持ってゆき、ゆっくりと口に含ませる。噛まずにしばらく、実を口のなかで転がしてみる。そして実を噛んでみながら、身体で実を食べている自分の経験を観察して、身体と心に起こる変化を観察していく。ゆっくりと噛み続けてから、呑み込み、その後、実が消化器を通っていく感覚や呑み込んだ後に残る感覚を観察してみる。
私の声の誘導を聞きながら、受講者はこのようにマインドフル・イーティングを実践する。ワークのあとにはグループでディスカッションを行い、授業後の課題ではさらに言葉で経験を丁寧に記述する。このほか、ゆっくり歩く実践や、目隠しをして気配を感じるワークなど、様々な一人称フィールドワークを授業で試している。
人類学的フィールドワークは、遠い未開の地に出向かなくても、日常のなかで実践できるということが、このようなワークを通して見えてくる。日々、見過ごしていることや、無意識で行っていることに、身体をともなって注意を向けていくと、「近い」ものを通して「遠い」ところへも旅ができるのであり、同時により「近く」、細やかに豊かに経験を味わうことができるだろう。身体的なモードで五感をひらき、一人称フィールドワークを行うと、毎瞬毎瞬を、新たな経験や景色として味わい尽くすことができるかもしれない。
1 Csordas, Thomas. 1993. Somatic Modes of Attention. Cultural Anthropology. Vol.8, no.2, pp.135-156.