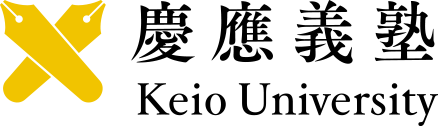20世紀以降の現代ドイツ文学を研究しています。最近は、文学テクストにおける歴史叙述の方法、特にドイツ語圏の作家たちが、世界大戦やホロコーストといった歴史的カタストロフの記憶をどのようにとらえ言語化しているのかに関心があります。
ことばが世界をありのままに伝えるものではないことに気づいてしまったモダニズムの作家たちは、新たな言語表現の可能性を求めてさまざまな言語実験を試みました。たとえば、アルフレート・デーブリーンというユダヤ系の小説家は、ナチス・ドイツ誕生前夜のベルリンを描くために、新聞記事、広告の文句、流行歌の歌詞、法律の文言、聖書や他の文学テクストからの引用、数式、統計データといった巷にあふれるあらゆることばを拾い集め、ときにはそれを加工して、自分の作品に組み込みました。今の読者には、どこからどこまでが作者本人の言葉なのかわかりづらい、出典なしのコピー&ペーストです。さらには、ドイツ語の文法や意味のつながりを壊し、工場で部品を組み立てるように、ばらばらになった言葉の断片をつなぎ合わせて大都市のスピードやダイナミズムを体感させる文体を生み出しました。壊すことにこのうえない快楽をおぼえたかつての前衛作家たちは、「私」が支離滅裂な存在で、人間の営みが筋だって説明できるような単純なものではないことを示すために、首尾一貫性のある語りの秩序を骨抜きにします。そこから浮かびあがるのは、もっともらしい物語でもって人々を支配しようとする権力や、同調圧力にあっさり屈してしまう民衆の姿でした。
すぐれた文学テクストには、作品が書かれた時代の価値観や世相のみならず、その時代のことばがきわめて研ぎすまされた形で保存されています。だからこそ伝えられる現実というものがあって、そうしたことばは時代や文化を超えても損なわれない強さを秘めています。テクストに織り込まれたことばの結晶や現実を見きわめて抽出するのが私の仕事です。日ごろ何気なく使うことばの限界を軽やかにのり超える文学テクストの言語は、慣れ親しんだ思考や行動様式を別の角度からとらえることを可能にします。そのように認識される世界はときにへんてこだったり不気味に見えることもありますが、それもまた現実のひとつの姿なのです。
デーブリーンは精神科の医者で、患者を診察するかたわら小説を書きました。日本でもいわゆる「理系」の小説家はたくさんいます。デーブリーンは、カメラの分解掃除をするようにことばを分解し、解剖する医者のまなざしでもって世界や人間を観察し、新しい言語表現の形を追求しました。理系・文系を区別する思考は受験が終わったら手放しましょう。学問に限界を設けるなんてナンセンスです。文理の知が混ざり合うところにこそ独創性あふれるおもしろいものが生まれてくるのです。理工学部にもひょっとすると小説家の卵が潜んでいるかもしれませんね。小説を書くのなら、まずは古今東西の作品をかたっぱしから読んで、みずからことばの実験を試してみてください。

Alfred Döblin (1878-1957):1930年ごろの写真(筆者私物のポストカード)