
この度、本欄に執筆する機会を与えて下さいました重野准教授に感謝いたします。簡単ですが、私の学生時代と会社に入ってからの研究内容について紹介したいと思います。
私は、1980年4月、慶應義塾大学の最後の工学部生として入学しました。「最後」というのは、翌年から工学部が理工学部に改組されたからです。日吉での2年間は、当時の流行に違わず、テニスをよくやっていました。授業の合間には大学食堂のたまり場に出没し、授業が終わればテニスコートに駆け付けていました。工学部の学生だけによるテニスサークルもありましたが、私は幅広く慶應らしさを味わおうと思い、敢えて他の学部も一緒のサークルに入りました。私が入ったサークルでは、慶應の内部進学者、地方出身者、当時では珍しい帰国子女など、理系文系を問わず様々な学生がおり、多彩な考え方に触れたことは、今思えば、社会の縮図を感じることでもありました。当時の学友との交流は、社会に出た今でも続いており、慶應で学んだ者だけが感じる一種独特な文化と豊かな学生生活を送れたことに、感謝の気持ちでいっぱいです。
3年になり、日吉から矢上の専門課程に移ったときには、数理工学科(現在の数理科学科)に進みました。4年の時は小畠・前田研究室に入り、小畠教授から代数幾何学のご指導を受けました。数理工学科に進んだ理由は、当然数学に興味があったからですが、それ以上に、数学は一番物事を論理的に考える学問であると当時学生ながらに思っておりましたので、この時しかできないことをしようと考え選んだ次第です。慶應の自由な雰囲気の中で、思う存分興味ある事柄について深く考え、問題意識を持つ姿勢やそれを解決する自分なりの方法論を身につけたことは、企業研究所に入ってから大変役に立ちました。
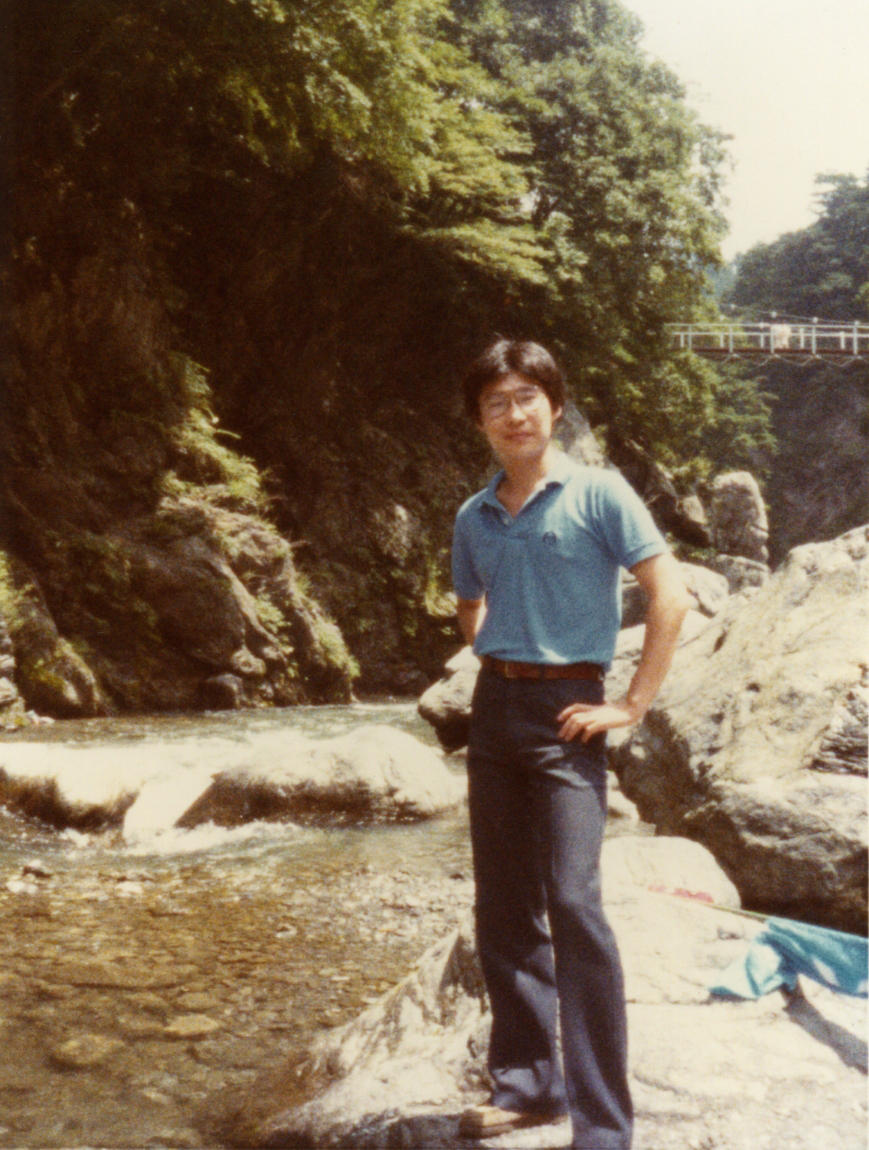
大学時代奥多摩にて
就職するにあたっては、企業の研究部門に行きたいと思い、当時世の中に出始めていたパソコンに関心があったことから、その方面の技術が進んでいて、研究所の施設も充実していた日立製作所に入りました。当時はまだパソコンの黎明期、OSがMS-DOSの時代で、入社間もなく米国マイクロソフト社に研修にも行きました。その後、PC-LANが世の中に現われ、一世を風靡したNetWareと呼ばれたネットワークOS関連の研究をすることになり、私が取り組んだ研究成果を製品化するために、米国Novell社を何度も訪れ、製品化にこぎつけました。これらの仕事の際には、外国人との付き合い方や問題意識の持ち方、それを解決する方法等、大学時代の経験が大いに役立ち、後に博士号を取得することにも繋がりました。
学位取得に当たっては、すでに数学の世界とは全く別のITの世界に身を投じており、自分の出身研究室とは異なる研究内容となっていたため、自分が所属する研究所が委託研究でお世話になっていた、当時計測工学科の松下教授にご指導いただくことになりました。私の場合、博士課程で学位を取るのとは違って、会社の仕事をしながら、それもちょうど会社勤めで一番油の乗ってきた忙しい時期に学位を取りましたので、制約された時間内での論文執筆はとても大変でした。このような状況においても、幸いなことに、松下教授も企業出身者であったため、私のように企業の仕事をしながら学位を取ることに対してのご理解があり、いろいろな面での御配慮をいただき、大変助かりました。さらに、その時一緒に相談に乗って頂いた岡田教授や重野准教授には、学位論文の書き方のコツから手続きに至るまで、大変お世話になりました。ここで、改めて感謝申し上げます。また、松下教授から、「ご家族の協力もあっての博士号取得であるので、是非授与式にはご家族共々出席なさってください。」とのお言葉を頂きましたので、そのようにしましたところ、家族としても、とても良い思い出となりました。
今も毎年、松下教授や岡田教授、重野准教授を囲んで「温故知新ドクターの会」を開催し、学位を取った者同士の親交を深めており、これも慶應ならではの集いとなっています。学位授与では、当時理工学部長であった、現在の安西塾長から「20世紀最後のドクターということで、非常に記念すべき年であり、今後も各界で頑張ってほしい」と直接のお言葉を賜り、学位記を頂いたのは今でも心に残っております。
博士号授与式にて妻と(2000年9月、三田)
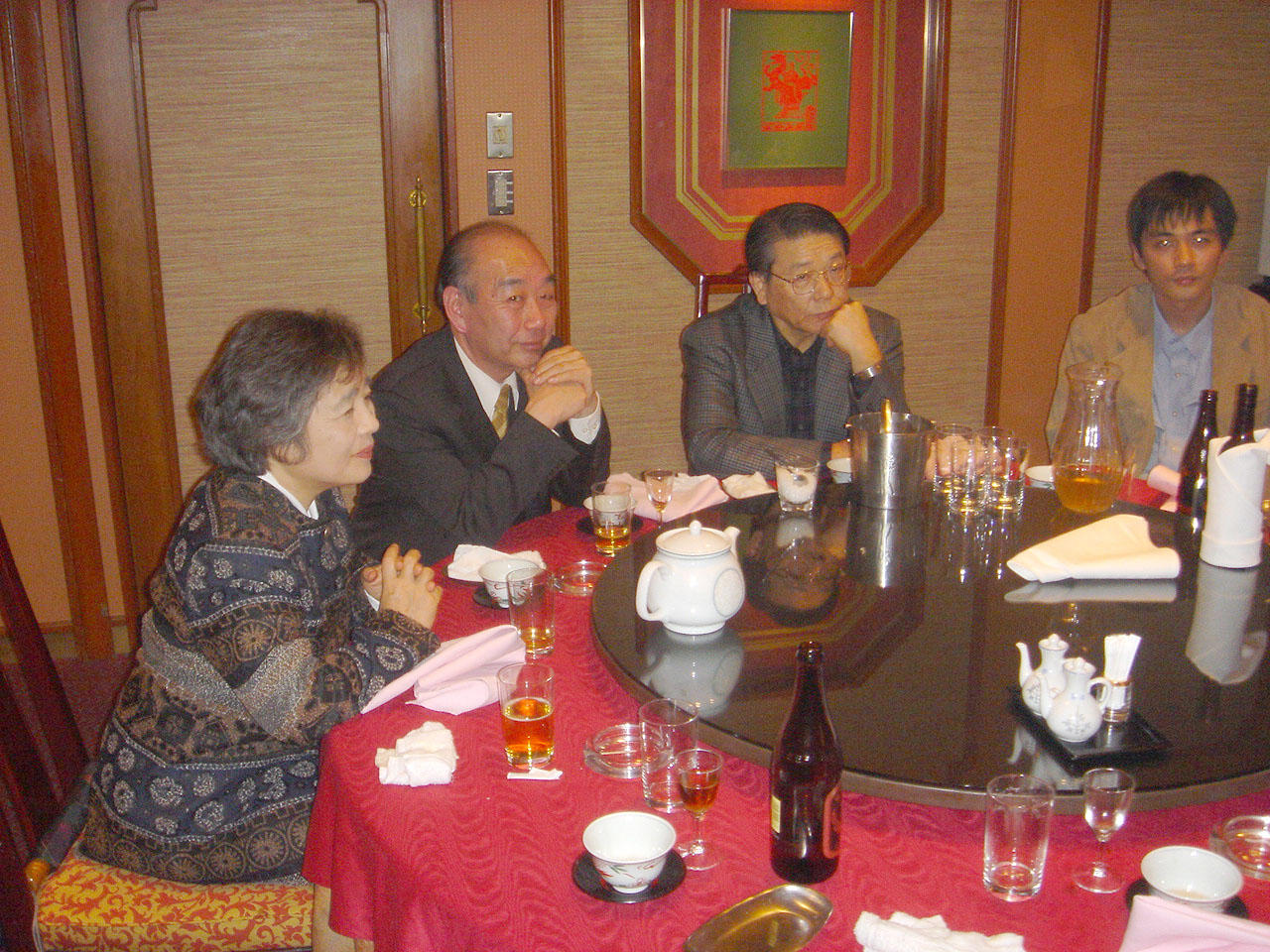
温故知新ドクターの会:恩師・松下先生(右から2人目)
さて、私が学位を取得し、まさにこれから落ち着いて研究に専念しようとした2000年に、政府は「電子政府」の政策を掲げ、私もそのプロジェクトに直接関わることになりました。当時の安西学部長が言われた、「各界で活躍してほしい」とのお言葉を実践できる良い機会が廻ってきたと、大変嬉しく思ったのを覚えています。
我が国では、2000年の「高度情報通信ネットワーク社会形成基本法(IT基本法)」の制定以来、官民を挙げてインターネットの利活用の促進に取り組み、「世界最先端の電子政府の構築」を施策として挙げ、まず初めに、「電子認証基盤(GPKI:Government Public Key Infrastructure)の整備」を掲げました。私は、この世界で最大規模の電子認証基盤のプロジェクトに参画しました。さらに、「電子署名法及び認証業務に関する法律」の制定委員に任命され、実際の法律制定に関与し、技術系の研究者としては極めて貴重な経験をすることができました。その後、経済産業省や総務省等と連携して、「アジアPKIフォーラム」「安心・安全インターネット推進協議会」「モバイルITフォーラム」等の民間フォーラムを次々と立ち上げ、情報セキュリティ分野からの取り組みとして、我が国の社会インフラに現在も貢献していることは、自分の研究人生において大変有意義なことと思っております。
最後に、今回の「塾員来往」執筆にあたり、自分の大学時代から現在に至るまで振り返ったところ、現在の自分の原点が慶應での研究活動とサークル活動に起因していることをつくづくと感じた次第です。慶應義塾大学の建学の精神である「独立自尊」を、一人の塾員として、世の中に広げていければと考えています。
プロフィール
手塚 悟(てづか さとる)
(長野県立上田高等学校 出身)
1984年3月
慶應義塾大学工学部数理工学科 卒業
1984年4月
株式会社日立製作所 入社
同社 マイクロエレクトロニクス機器開発研究所 配属
1993年4月
研究所統合により、システム開発研究所 所属
1995年2月
システム開発研究所 主任研究員
1999年2月
システム開発研究所 浜松町分室 室長
2002年8月
システム開発研究所 第7部 部長
2007年10月
システム開発研究所 シニアマネジャ
現在に至る
◆受賞
平成16年度 情報処理学会論文賞(2005年5月)
平成18年度 関東地方発明表彰 発明奨励賞(2006年11月)
IEEE IIHMSP2006 Best Paper Award(2006年12月)


