
このたびは、理工学部や私のコラムに興味を持っていただきありがとうございます。受験や進学を検討している皆さんが、大学で何に取り組むかのヒントになれば嬉しいです。
「興味を軸に自由なキャリアを築く」
最初に自己紹介をさせていただきます。私は約20年前に物理情報工学科を卒業しました。現在は自分の事業を含めて複数の仕事をしており、大きく分けて二つの分野があります。一つは企業向けコンサルティング、もう一つは教育機関などを中心とした宇宙分野です。宇宙分野では、慶應義塾大学の理工学研究科やシステムデザイン・マネジメント研究科の学生向けに「宇宙システム工学」の講義を担当しています。また、キッザニア東京や全国の学校で中高生向けに衛星データを使った地球観測について講演やワークショップを実施したり、『いちばんやさしい衛星データビジネスの教本』という書籍も出版しました。さらに数年前まではJAXAの非常勤招聘職員として企業における宇宙ビジネスの推進を行っていました。

一見「企業向けのコンサルティング」と「中高生含めた宇宙に関する教育」という二つの領域は関係が薄いですが、どれも自分が情熱を持てるテーマであり、自由に様々なプロジェクトに取り組める働き方に幸せを感じています。時にはJAXAでの仕事のように宇宙とビジネスが直接関連することもあります。この自分の興味に沿って複数の仕事に取り組む働き方の原型は以前勤務していたGoogleにて構築しました。ただ、興味のある分野そのものは大学時代に培い、現在に繋がっていると思います。
Googleで勤務していた際には、メインの仕事は企業向けに最新技術を用いて新しいソリューションを企画したり構築するコンサルティングでした。ご存知の方もいるかも知れませんが、Googleでは「20%ルール」という制度があり、メインの仕事以外に自身が重要と思う取り組みに20%の時間を割いてよいのです。もちろん企業なのでメインの仕事で成果をきっちり出した上で20%に取り組むという厳しさもあるのですが、テーマは自由でした。そこで私はこの制度を活用して、Google Earth Engineという衛星データなどを分析できるプロダクトを国際機関や大学、NGO、NPOなどのパートナーと共に国際的に普及促進するという仕事にも取り組みました。この時の20%ルールを活用した経験が現在の性質の違う複数の仕事を自身の興味やお客様のニーズを踏まえて自由に進めるという働き方につながっています。

「大学という自由な実験場」
私の場合、現在に繋がっているグローバルな環境で仕事したいという考えや、幼少期からの宇宙への好奇心を深めたのは大学時代だと考えています。ご参考までに、いくつか私の学生時代の経験を紹介します。
大学に入学してすぐに感じたのは、無限に探検できる自由な世界が広がっているという感覚でした。日吉キャンパスでは無数のサークルが新入生を募集しており、新しい分野に気軽に挑戦できました。例えばよほどのマンモス高校では無い限り、同級生は知っている人ばかりだと思いますが、大学では様々なコミュニティにどれだけ参加しても、常に自分の知らない多様な人々がおり、自分の視野が大きく広がったのを覚えています。
私は国際交流などに興味があったので、当初そのようなサークルを中心に活動をしていました。ところが、主に大学の留学生たちと交流するところが多い中、忘れられているグループがいることに気が付きました。それは、日本語学校の生徒です。当時、日本の大学に入学する前に早めに来日して、1年程度予備校のような日本語学校で学んでから大学に入学する留学生が多かったのです。そして、これらの日本語学校の生徒は母国を離れ、日本に飛び込んできているにもかかわらず、日本人と交流する機会は限られていました。
そこで慶應義塾大学の友人だけでなく、他の大学の友人も含めて同じ課題意識と情熱を持っている人を集め、日本語学校の生徒と交流するサークルを立ち上げ、初代代表として活動しました。当時高田馬場にて点在していた日本語学校を訪問し、生徒募集を行い、多くの留学生と日本の学生の交流を促進できました。サークル自体は無くなってしまったのですが、今でもメンバー間で友人関係が数多く続いています。また、グローバルに様々な方と関わりたい、という自分の考えも明確化され、Googleでの勤務や米国でのMBAなどに繋がったと思います。
今思えば、慶應義塾大学の学生という立場と環境に助けられ、多くの方とコラボレーションできたのだと思います。このように大学時代は、自由な実験の期間と捉えて、失敗を恐れず興味を持ったことに積極的に挑戦する絶好の機会です。最近は企業による学生限定プログラムや起業支援も充実しているので、活用するのも一つの選択肢だと思います。成功してもしなくても、得られる学びや友人は貴重な財産になるはずです。
「10年越しの好奇心がキャリアを拓く」
もう一つお伝えしたいのは大学卒業後、すぐにキャリアに繋がらなくても、ご自身の興味は長期的に大事にしておくと良いと思います。例えば、私は子どもの頃から惑星探査に興味がありましたが、当時の理工学部には直接的な研究室がなかったため、核融合プラズマの研究を行っている畑山明聖教授の研究室に入ることを決めました。小惑星探査機「はやぶさ」で有名となったイオンエンジンと共通する要素もあったからです。畑山教授はこのように柔軟に私の興味に寄り添ってくださり、さらに研究室では先輩方や同期からの指導や協力がありました。深夜に長い時間をかけたコンピュータシミュレーションが止まったりと、大変な中にも楽しい思い出がたくさんあります。
学部を卒業後、惑星探査の研究に携わるため、東京大学大学院の理学系研究科に進学しました。理学系研究科では、日本の惑星探査ミッションを主導している宇宙科学研究所(現JAXA)に所属し、研究することができるからです。幸運なことに宇宙研では当時の日本惑星科学会の会長で、月探査ミッションなどを推進されていた水谷仁教授の研究室に配属になり、アポロ16号が持ち帰った月の砂(レゴリス)などを用いて、月のリモートセンシングの研究をしました。ちなみに水谷教授は、退官後に雑誌『ニュートン』の編集長となり、先生のコメントを雑誌を通じて読むのも楽しみでした。
実はリモートセンシング分野からは修士修了後離れてしまっていたのですが、その知識は10年以上後にGoogleで衛星データの仕事をする際に役に立ちました。さらにGoogleでの仕事がJAXAでの仕事や慶應義塾大学で講義を持つことにつながりました。このように興味を持ちづつけていると思いがけず様々なご縁やキャリアにつながっていくこともあります。
以上、私の経験を少し紹介させていただきました。皆さんが大学生活を通じて自由に興味を探求し、それを大切にしながら自分らしいキャリアを築いていけることを願っています。
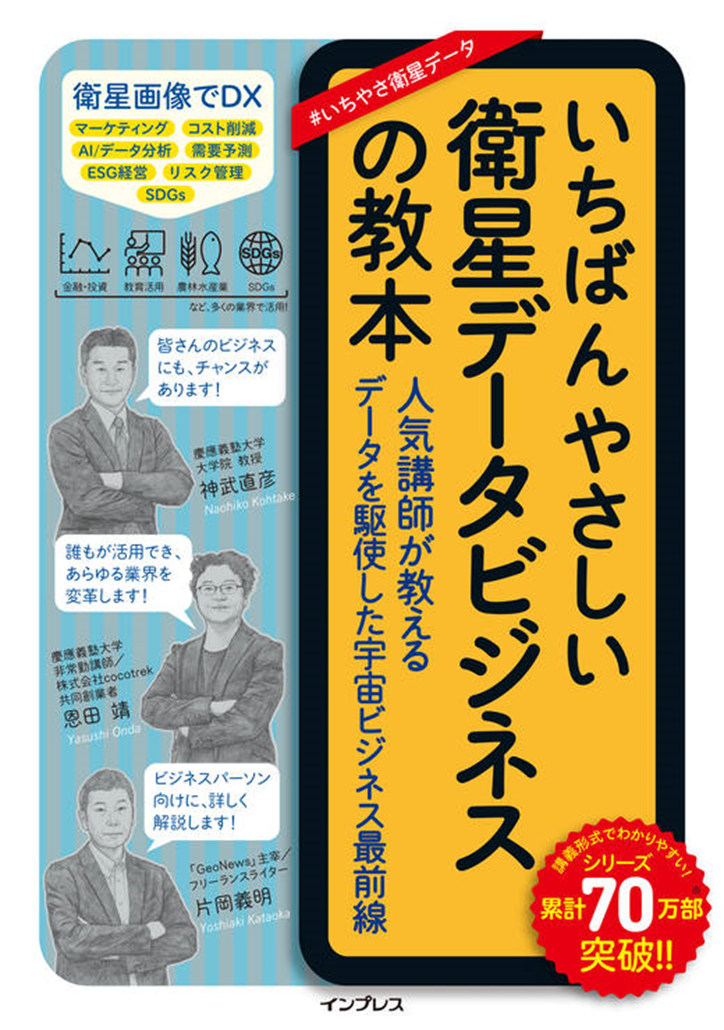
プロフィール
恩田 靖(おんだ やすし)
(慶應義塾湘南藤沢高等部 出身)
2002年
慶應義塾大学 理工学部 物理情報工学科 卒業
2004年
東京大学大学院 理学系研究科 修士課程 地球惑星科学専攻 修了
2015年
Carnegie Mellon University, Tepper School of Business 経営大学院修士課程 修了 (MBA)
2004年
株式会社NTTドコモ 入社
2015年
Google LCC 入社
2020年
独立 / 株式会社cocotrek
現在に至る


