進路選択

高校の頃から数学と物理が得意でした。高校の同級生から「大学教員になれば数学や物理を研究して食べていける」という話を聞いて、単純な私は進路を決めました。物理ではなく数学を選んだのは、数学の方が得意だと感じていたからです。インターネットが普及していない頃の田舎育ちであれば、進路の選び方なんてこんなものです。
学部生時代
慶應義塾大学理工学部学門 2 に入学して数学を学び始めると、高校までの数学との違いに驚かされました。高校数学の延長だろうと甘く考えていました。正直なところ、学部 1 年生の講義では大学数学の面白さが分からなかったのですが、せっかく数学を勉強しようと入学したのだから最後までやり切ろうと思い、数理科学科に進みました。2 年生になると講義とセットで演習が開講されるようになり、演習問題を解いているうちに大学数学の面白さや奥深さを実感するようになりました。特に、高山正宏先生の演習では、答案を提出すると赤ペンで丁寧に添削してもらえ、とても勉強になりました。この頃、数学研究会というサークルがあると知って入会することにしました。このサークルで、第 142 回塾員来往を執筆された同級生の山田君と親しくなりました。サークルメンバーと一緒に夜遅くまで、空き教室でセミナーをしていたのは良い思い出です。3 年生になると講義は専門性が増してきました。恩師である谷温之先生が担当された関数方程式概論では、数学の定理だけでなく、その背景にある物理現象なども論じられました。研究室配属では、物理現象に焦点を当てた数学を研究したいと思い、谷研究室を選びました。谷先生からの最初の問いは「君はどの現象に興味があるの?」でした。先輩たちは、地震、水の波、超新星、台風、泡などを数学的に解析していると聞いて、とてもワクワクしたのを未だに覚えています。後日、谷先生に「雷に興味がある」と返答しました。今となれば夢みがちだったと思うのですが、このときの選択が大きな分岐点となりました(後半で詳しく述べます)。
数学以外では、慶應かるた会という競技かるたのサークルにも参加していました。当時は、漫画「ちはやふる」が流行るだいぶ前だったので、会員数は少なかったのですが、そのぶん会員同士とても親密でした。先輩やOB は、貧乏学生であった私に夕ご飯を奢ってくれました。その代わりに、終電を逃した会員を、私が下宿していたボロアパートに泊めたりしていました。みんなで参戦した職域(競技かるた団体戦の大会) も良い思い出です。また、数理科学科では、愉快な同級生にも恵まれました。当時、矢上キャンパスで昼食をとれるのは生協かカフェテリアしかなく、お世辞にも恵まれた環境ではなかったのですが、同級生と食べる昼食は、大学生活における楽しみの一つでした。また、同級生との卒業旅行では、18切符を使って全国各地のグルメを食べながら、日本三景を見て回りました。宿泊先は漫画喫茶(1 泊 1500~2000 円、シャワー利用可) にして、予算を食費に全振りしました。下関では河豚を、神戸では神戸牛を食べたのですが、どちらもとても美味しかったのを未だに覚えています。

卒業後
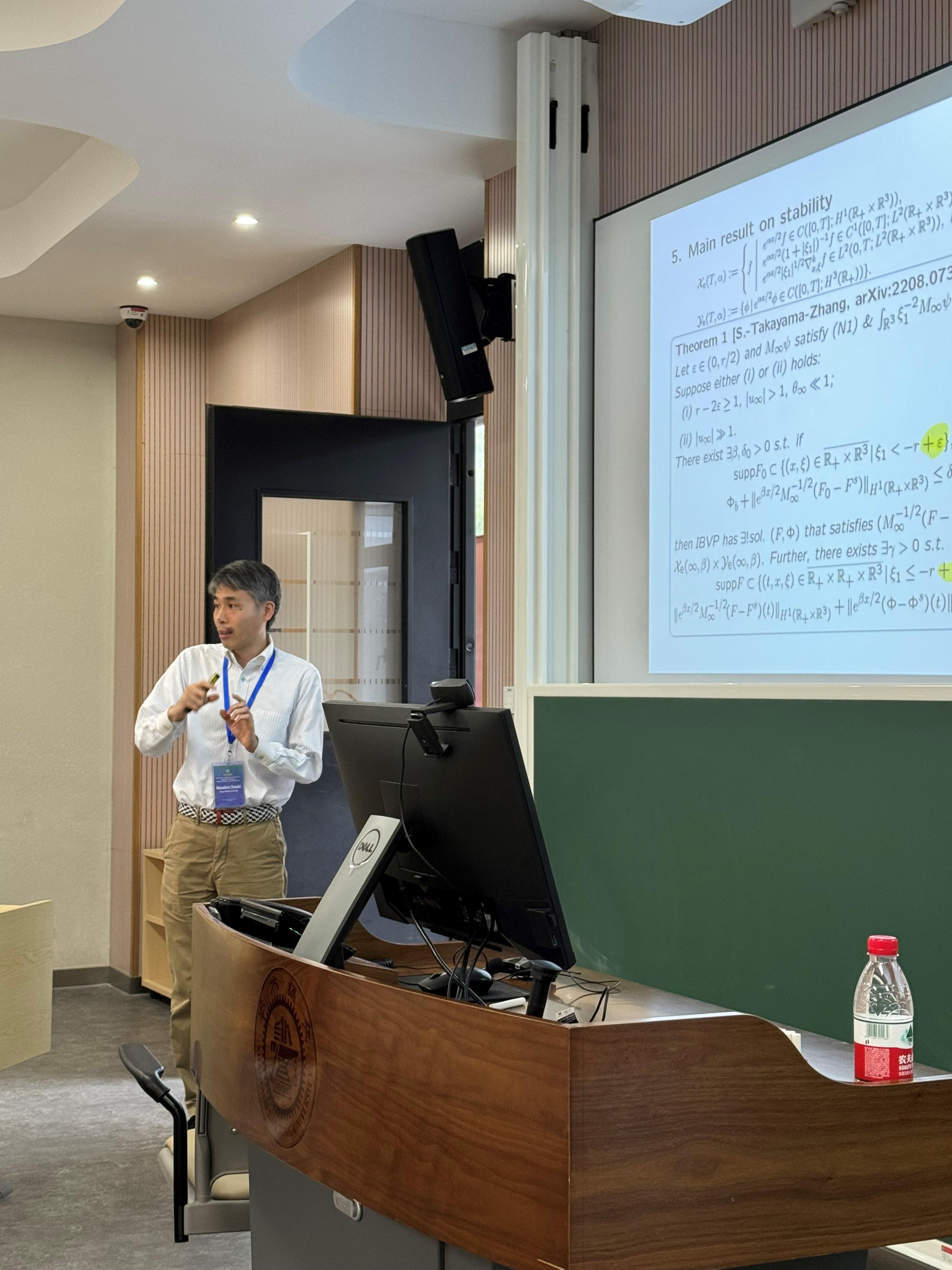
慶應義塾大学を卒業後は、東京工業大学の大学院に進学しました。もちろん谷先生のもとで勉強したいという気持ちはあったのですが、学費が安かったのと、外の世界にも触れたくて東工大を選びました。ただ、東工大と慶應大は目と鼻の先で、よく慶應大に遊びに来ていました。いいとこ取りした感じです。東工大で博士号取得後は、学振特別研究員、早稲田大学 助手(裏切り者と罵らないで下さい)、東京工業大学 助教を経て、現職の名古屋工業大学 准教授に至ります。この間約 20 年ずっと、プラズマにまつわる諸現象を数学的に解析していて、とくに放電も取り扱っています。ただ、放電といっても実験室で起こるものまでしか解析できておらず、自然界で起こる雷までは未だに辿り着けていません。(研究内容に興味がある方は、 http://suzuki.web.nitech.ac.jp/summary.html をご覧下さい。)学部生時代に抱いた興味がこんなにも研究者人生に影響するとは、自分でも驚きです。もちろん、この間には色々な出来事がありました。特筆すべきことの一つは、名工大の在外研究員制度に採択されて米国のBrown 大学に約 1 年間滞在したことです。平日は研究に没頭し、週末は米国の文化に触れ、貴重な体験をさせて頂きました。また、新しい友人も沢山できました。こうした良い面のみを述べると、冒頭で記述した命題「大学教員になれば数学や物理を研究して食べていける」があたかも真であるかのように錯覚しますが、現実はそんなに甘くありません。ほとんどの国立大学では、教育、研究以外の大学運営業務や雑務が増加していて、教員自身が工夫して研究時間を確保する必要があります。こうした状況にもどかしさを感じることはありますが、興味を持って取り組んでいた研究課題を成し遂げたときの達成感は計り知れなく、頑張り甲斐があります。 先に登場した谷先生や高山先生とは共同研究を行なっていて、頻繁に連絡を取り合っています。年に 1 度は、谷先生のご自宅にお邪魔してセミナーをしています。毎回、夕食後も討論させてもらうのですが、話が尽きることはなく結局午前 2 時頃に解散となります。また、高山先生に会うため、年 1 回ぐらい矢上キャンパスを訪問しています。矢上はセブンイレブンができて便利になりました。研究集会に参加した際には、谷研OB と会うこともあります。みんなもう若くはありませんが、深夜まで研究談義が白熱することも珍しくありません。また、かるた会の会員や数理科学科の同級生とは、今でも一緒に夕ご飯を食べに行ったり、旅行したりしています。

こうして思い返してみると、慶應義塾大学在学中にこんなにも多くの生涯の恩人・友人に巡り会え、入学して本当に良かったとしみじみと感じます。このかけがえのない出会いを与えてくれた慶應義塾に感謝いたします。また、文末になりましたが、数理工学科から数え、数理科学科設立 50 年、心からお祝い申し上げるとともに、今後さらに大きく飛躍されますよう祈念いたします。
プロフィール
鈴木 政尋(すずき まさひろ)
(静岡県立富士高等学校 出身)
2004年3月
慶應義塾大学 理工学部 数理科学科 卒業
2006年3月
東京工業大学 大学院情報理工学研究科 数理・計算科学専攻 修士課程 修了
2009年3月
東京工業大学 大学院情報理工学研究科 数理・計算科学専攻 博士課程 修了
2009年4月
日本学術振興会 特別研究員PD (東京工業大学 大学院情報理工学研究科)
2010年10月
早稲田大学 非線形偏微分方程式研究所 研究助手
2011年4月
東京工業大学 大学院情報理工学研究科 助教
2016年3月
名古屋工業大学 大学院工学研究科 准教授
現在に至る


