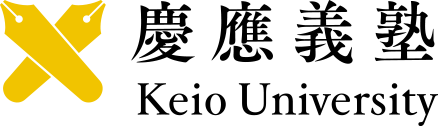世の中には、実験にまったく向いていない、という人種が確実に存在する。かく言う私がそうである。道を歩けばその辺にぶつかる。座れば周囲のものを落っことす。手にしたものは置き忘れる。こういう人間が実験系の研究室にいると、誠に迷惑である。装置は当然のごとく動かないし、たまに動くとすぐ止まる。止まるといえば聞こえがいいが、要するに壊しているのだ。研究者の道を進まず新聞記者に転じたのは、思えば賢明な選択であった。


1991年に私は物理学科の大学院を出て、日本経済新聞社に入社した。そして脳死臓器移植やエイズ、薬害といったテーマを取材した。人の人生に直接にかかわる医療の取材はやり甲斐があった。英の大学院で医療経済学を学び直したりもし、自分は医療記者としてまっとうするのだと信じていた。
だが新聞記者とてサラリーマンだ。2001年の人事異動でIT分野の担当を命じられ、図らずもこの世界に戻ってきた。
久しぶりに足を踏み入れた物理と工学の世界は、医療に比べるといかにも退屈に見え、内心がっかりしたが、その年の夏、次の転機が訪れた。休暇で訪れた英オックスフォードで、最近注目を集めている未来の超高速計算機、量子コンピュータの理論を提唱したデイヴィッド・ドイチュ博士に会ったのだ。

新聞記者の駆け出し時代。完成したばかりの高速増殖炉もんじゅを取材。
軽い気持ちで訪れたのだが、彼の自宅を一目見た時から、何かが起こりそうな予感がした。まるで空き家だ。ドアのペンキは剥げ、窓のカーテンは色あせ、庭には草がぼうぼうと茂っている。呼び鈴を押してドアが開くと、今度は壮絶な散らかりように息を呑んだ。あらゆるものが床を覆いつくし、階段をはい上り、隅という隅を埋め尽くしている。その中に、華奢な長身によれよれのシャツを着て、肩につきそうな長髪のドイチュ博士が微笑んで立っていた。
後にわかったことだが、博士は講義をせず、試験もせず、大学に足を踏み入れない。その代わりに給料も貰わず、もっぱら自宅で研究している。「どうして量子コンピュータは早いんですか」と聞くと、「僕の考えでは、平行して存在する多数の宇宙で計算を分担しているからです」ときっぱり言い切った。
彼の話は当時の私にはまったく理解不能だったが、不思議と忘れがたかった。私はこの突飛なコンピュータについてもっと知りたいと思い、週末や休暇を使って、各国の研究者を訪ね歩いた。何かが見えてくるたびにドイチュ博士を再訪して議論し、気がつけばすっかりのめりこんでいた。新聞で書ける範囲をたちまち逸脱し、記事にできる当ては全然なかったが、私は遮二無二取材を重ねた。
すると良くしたもので、この稿を書いている2004年に新聞から日経サイエンスという科学誌の編集部に異動した(写真)。科学好きの人々のための娯楽誌で、宇宙論や生物進化など、新聞ではめったに取り上げることのない話題が豊富に載っている。塩漬けになっていた3年間の蓄積を蔵から出すように、私は徐々に書き始めた。
そうこうするうち他からもお座敷がかかるようになり、2つの雑誌に量子コンピュータの発明物語を書いた。1つは「アリエス」という講談社の新雑誌で、もう 1つは——物理学会誌である(写真6)。2004年8月号、題して「2つの悪魔と多数の宇宙:量子コンピュータの起源」だ。研究者の卵だったころ、物理学会誌に自分の書いた記事が載ることなど、想像もできなかった。卵は結局孵化しなかったが、不思議なめぐり合わせで今、それが実現している。放蕩息子が家に帰ってくるように、再び物理の話に夢中になってしまったのは、大学時代に培われた何かが自分の中のどこかに残っていて、私を呼んだのかもしれない、そんな風に思ったりもするのである。

英国ヨーク大学留学中、同じ学科の仲間たちと

記事が載った「日本物理学会誌」(2004年8月号)の表紙

日経サイエンス編集部にて勤務中
プロフィール
古田 彩(ふるた あや)
(神奈川県立柏陽高校 出身)
1989年3月
慶應義塾大学理工学部物理学科 卒業
1991年3月
慶應義塾大学大学院理工学研究科物理学専攻 修了
1991年4月
株式会社日本経済新聞 入社
科学技術部の記者となる
1995年7月~ 1996年10月
英国ヨーク大学 留学
1998年3月~ 2001年2月
英字新聞Nikkei Weekly 編集部
2001年3月~ 2004年2月
日本経済新聞 科学技術部
2004年3月
日経サイエンス 編集部
現在に至る